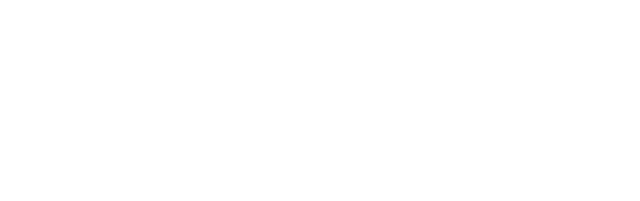満足度の高い研修が行動変容度が高いとは言えない
2013年10月3日(木)
今日の富士山には薄い雲がかかっています。もう秋の雰囲気です。

さて
昨日は、ある企業に行って人材開発の方々と商談をしていました。
その企業では、現在4つのテーマが上がっており、その1つが「研修の効果測定」だそうです。
現在、研修を受けたことがある従業員に
「その研修が効果があったか?」
という質問をインタビューして回っているとのことでした。
私は、
「その質問は怪しい」
とコンサルティングしました。
「この研修は有効的でした。」「この研修は有意義でした」「この研修は役に立ちました」
という回答を得て何が良いのでしょうか。まったく価値がありません。
なぜなら、研修の目的は、研修の後、職場に戻ったあとの
「行動変容」
だからです。よって
どのように行動が変わったか? を聞かずして意味のないインタビューとなってしまいます。
研修後のアンケートの満足度が高く、満足している講師や人材育成部門の方々を見ます。
いったいそれでいいのでしょうか。
私が持っている行動定着のデータをみても、満足度の高い研修が行動変容度が高いとは言えないのです。
なぜでしょうか。
行動するかどうかは
・目標設定の正しさ
・行動習慣の計画
・内省の技術習得
・お互いのフィードバック
・継続するための仕掛け
などPDCFAサイクルがひとつの解となります。今までの研修技術だけでは足りないのです。
今月、産労総合研究所さんの「企業と人材」という月刊誌の10月号より私の記事が掲載されています。
タイトル「目標達成のための行動習慣化メソッド”PDCFA”サイクルの考え方と実践」
で12回連載となります。
HRD担当者向けに分かりやすく書いていますので楽しんで読んでもらえたらと思います。
さあ
今日も元気に「いってらっしゃーい」